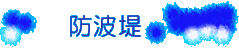身体障害者施設○△は、海岸にせり出した小高い丘の上に建っている。僕の部屋からは、ベッドに横たわったまま、広い窓いっぱいに土佐の海を一望することができる。絶景だ。おのずと毎日海を眺めて暮らすことになった。
福島県南端の海岸べりに四ッ倉という町がある。地図を広げて、海岸線に記された文字や記号を、一つ一つ指でなぞって探しでもしないと、見落としてしまいそうなシミのような町である。けれども、この町は素晴らしい海を持っていた。真っ白な広い砂浜、延々と続く深い防砂の松林、海は深くて色濃い。人っ子ひとりいない砂浜を波だけが暴力的に打ちよせていた。
松林に守られて点在する家々は、長い間の浜風に耐えてきた古家ばかりである。原色などどこにも見あたらない、時代に取り残された町だが、過疎地に見られるような暗さはなく、まるで町全体がハレ−ションを起こしたように、どこへ行っても明るく眼に痛いくらいである。それは、砂混じりの大地が太陽光線を反射させているためだ。一見危うそうな砂上の町だが、もう幾十世代にもわたって、人々は何ごともなくおだやかに暮らしてきた。一粒一粒の白い砂の集合は、人々に知らず知らずのうちに至福の生活を与えてきたのだった。
僕は、小学校入学前の一年間をこの地ですごした。父の姉の嫁ぎ先で、伯母は豪快な笑い声をあげる温かな人だった。この地の人々はどの顔も黒く日焼けし、解放的でくったくがない。ちょっと外出すると、いたるところから声をかけられ、人なつっこい顔にお目にかかることができた。
土佐の海は、太平洋に懐をひろげているにもかかわらず、日々、穏やかな表情を見せてくれる。
水面が揺れて泡立っている。それは無数の命が誕生しているかのよう。
キラキラと輝いている。それは膨大な数の昆虫が発光しながら水面すれすれを飛び交っているかのよう。
水面の色合いが微妙にちがう。それは昨夜の空をブル−でコピ−した天の川のよう。
―― 東京の生活に疲れた僕は、ふいに、上野駅から<ひたち41号>に乗った。突然の訪問にも伯母は破顔で迎えてくれた。なつかしい家でひとこごちついたころ、近所の人々が入れかわり立ちかわりやってきて「大きくなった」「立派になった」と、独りになりたい僕を離してくれなかった。僕はひさしぶりに、騒々しい、けれども嬉しい一夜をすごした。
翌日、浜へ出かけた。二十数年ぶりである。ところが昨夜は気がつかなかったのだが、外へ出てみて驚いた。記憶の中の風景とはあまりにも違っていたからだ。伯母の家から浜までは、わずか二百メ−トル足らずなのだが、その間の、昔は広大なラッキョ畑だった砂地に、貧相な建て売り住宅が建ち並び、大型看板が林立し、二本のコンクリ−トが無粋な色をさらして延び、風情をだいなしにしていた。一本目のコンクリ−トは町を分断する国道で、ひっきりなしの大型トラックが騒音と排気ガスを撒き散らしていた。
僕は、トラックの切れ目をついて向こう側へわたり、昔のままの姿をとどめる松林へと足を踏み入れた。松林を抜けると真っ白で広々とした砂浜がひらけているはずだった。が、目の前には二本目のコンクリ−トの高い壁が行く手をふさいでいたのだった。防波堤である。僕はしかたなく壁にそって歩き、あきらめかけたころやっと階段を見つけて堤防の上に立った。そして再度、失望を味わされたのだった。堤防の下には巨大なテトラポットがうず高く積み重ねられていたからである。あの、幅が百メ−トル以上もあった白浜はいったいどこへ行ってしまったというのだろうか。悠久の砂浜が消え去るはずもない。削り取られたに違いないのだ。東京から仙台まで伸びる国道の一部にでもなってしまったのだろうか。
かつて僕は旅行好きだった。関東一円をはじめ、目的もなく、よくあちこちをうろつきまわったものだ。そう思って改めて考えてみると、どこの海辺へ行っても堤防にぶつかった記憶がある。まるで日本国中の海岸線をコンクリ−トの壁で囲ってしまったかのようである。そして、それはそのまま、僕たちの日常に合致してきた。高波を防ぐはずの防波堤も、いまや人と人とを仕切る壁となるばかりで、荒れはて続ける心の侵食を防ぐことはできていない。安全や便利さの代償として僕たちが失ったものは計り知れないほど大きいのかもしれない。
世はニュ−サイエンス・ブ−ムである。科学万能に裏打ちされた合理主義を徹底的に押し進めた結果、たしかに僕たちの生活は、津波の危険も少なくなって向上したかにみえる。ほしいものは何でも手にはいる。けれども人間中心の自然破壊は、大量の核の保有とあいまって、いまや地球規模の大津波の危機を引き起こしてしまっている。
僕らは、そろそろ、ほんとうに気がつかなくてはいけないのだ。ほんとうにほしいものは、それぞれの内にあるということを――。僕が歩けなくなって、伯母のやさしさに思い至り、逢いたいと思ったとき、伯母はもうこの世にはいなかった。案外、僕たち頚損者がいちばん近い所にいるのかもしれない。
窓外に真っ青な海がある。松林がある。砂浜がある。白鷺が遊んでいる。海では、そのほんの少しの恵みを得るべく漁船が数隻漂っている。これ以上、何の不足があろうか。それなのに、つい最近、この残された自然あふれる土佐の浜にも、竣工船の粗忽な音が響いている。人間の欲望は懲りることを知らない。
ー '87・2 ー