自然の色>七色の虹>虹の原理
虹の原理(3)
「虹 その文化と科学」(西條敏美 恒星社厚生閣)に、その原理についての解説があったので、紹介したい。計算・グラフ化はエクセルを活用した。雨粒の半径をR、入射光線と雨粒の中心を通る軸との距離をx、入射角i、屈折角r、屈折率nとする。
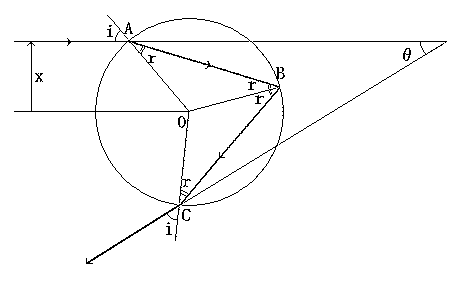
角θは図より(是非確認してみてください)
θ=4r−2i ・・・(1)
スネルの法則より
sin(i)=x/R ・・・(2)
sin(r)=sin(i)/n=x/(R・n) ・・・(3)
逆関数を取ると、
i=arcsin(x/R) ・・・(4)
r=arcsin(x/(R・n)) ・・・(5)
式(4)(5)を式(1)に代入すると、θが求まる。
θ=4arcsin(x/(R・n))−2arcsin(x/R) ・・・(6)
エクセルで、n=1.33(赤色の屈折率)、x/Rは0.01刻み(0から1)の値を次式に代入し、θを求め、グラフ化した。
θ=ROUND(4*DEGREES(ASIN([x/Rの数値セル]/1.33))−2*DEGREES(ASIN([x/Rの数値セル])),2) ・・・(7)
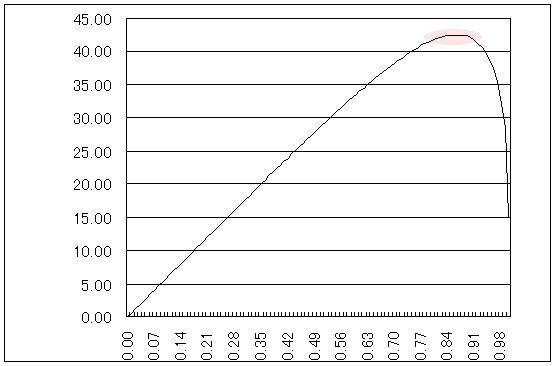
グラフは、横軸がx/R 、縦軸がθである。x/R=0.86 付近でθが最大(42.51°)であり、θ=42° 付近の光が他に比べて多くなっている。
太陽光等の平行光線は、水滴に衝突すると42°付近で収束(光が集まる)する。この収束の角度は、光の波長により少しずつ異なり、このことにより虹が見えるというわけだ。
(2005/6/12、TAKA)
虹の原理(1)|虹の原理(2)|虹の原理(3)|虹の原理(4)|7色の虹に戻る
トップページへ