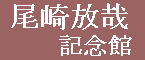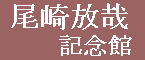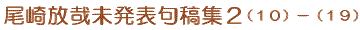 [句稿集3へ] [句稿集3へ]
句稿(10)
層雲雑吟 尾崎放哉
※○島の祭
盆燈篭の下ひと夜を過ごし古郷立つ
うら盆の田舎の町となり逗留して居る
少し病む児に金魚買うてやる
夕陽松の葉をわけてさし込む
牀の木の水嵩に提灯一つ吊るされ
鶏頭切ってやる実をこぼし
下駄の鼻緒たてゝ揃へられたる
葡萄喰べあいたとハガキよこした
風吹く家のまはり花無し
年寄りに道を教え晩が来た 放哉
足袋が片ツ方どうしても見つからない
なんでもない事の人だかりであった
どうかすると蜘妹の糸が光る窓だ
線香が折れる音も立てない
藤棚から青空透かして一日居る
鬼灯がまっ赤な女の家に来て居る
これで葬式を二つ出した戸口だ
青田道もどる窓から見られる
芋が白い芽を出して居る土間だ
日なたに筵を持ち出して里の児がかたまってゐる 放哉
山は海の夕陽をうけてかくすところ無し
家が建てこんで来た町の物売りの声
水を呑んでは小便しに出る雑草
障子を少しあけて見る雨がやみそうもない
とり籠餌を残して死んだ小鳥
山かげの赤土堀って居る一人
屋根の棟に雀が並ぶあちむくこちむく
棹を櫓に代へる広々と出にけり
船の中の御馳走の置きどころが無い
いやな雲が覗いて居る山のうしろ 放哉
しゃぼん一つ置いて買え買え云はれてゐる
花火があがる空の方が町だよ
一本しかない足を虫等に投げ出してゐる
犬の顔つくづく見て居るひまがあった
口もあけないあけびを一つもって山から下りる
ふところ手して居る朝の山明けきった
温泉の町煙りをあげて月夜
一疋の蚤をさがして居る夜中
祭の大太鼓がなる海風
なつかしい角帯をしめきちんと座って見る 放哉
道を教えてくれる煙管から煙りが出てゐる
旧道静かなる家家人住み
をくれて来た一人を乗せて舟出す
君が呼ぶ声に障子をあける
梅の実拾って子供になんべんも通はせる
みんなが広ろ間で勝手に寝てしまった
灰かぐらのなかからひげもぢゃの顔が出た
海風に呼吸を押し込まれて歩く
散歩に出る杖かるく草ひく人居る
木槿の花がおしまひになって風吹く 放哉
裏口からはいる気安さで来て居た
障子をしめてある縁に朝の日さし
わらじはきしめ四五人にまだ明けきらない
鵙がなくいつも見て居る大松
芝居のはねの雨の灯の町
傘をかついで行く広ろびろ虹たつ
雨の糸瓜見て家にばかり居る
わが熱を見る君の脈を借りる
稲田みだれ伏す星が消え行く
朝起きた手のしびれが残って居た 放哉
句稿(11)
層雲雑吟 尾崎放哉
菊つくる小器用な若い夫婦
糸瓜の棚つくるすっ裸になって居る
長雨のあと大きな夕陽の顔が一つ
返事を返してゐるひまに雲なし
橋の半分頃まで来て呼ばれて居る
三人で笑ってどれもよく呑む
花売り花こぼし遠く行きけり
今日も来てしまった松の根もとにかゞまる
追っかけて追ひ付いた風の中
とうとう見えなくなった一羽の烏見てゐた
なにくれとして居る窓でだまって月が出てゐた
月がだんだん登って行って小さうなった
海が入り込んで来て居る限り月に光り
ぴったりしめた穴だらけの障子である
思って居た通りの枝に烏がとまった
一つたべてしまった梨子の心がある
烏の羽音を間近かに聞いて暮れかける
ワィシヤツまくり上げて山ほど仕事がある
さよならなんべんも云って別れる
あけがたとろりとした時の夢であったよ 放哉
ばたりと風が落ちた夜の襖をあける
足のゆびばかり見て急いで歩く
案山子の顔をこう書いてやらう
路次の奥までさかなやの声が通る
風呂しきのなかが御馳走らしい
をそい月が町からしめ出されてゐる
門を出てから右左にわかれた
巡査のうしろから蜻蛉がついて行った
蜻蛉がみんなぱっと立ったいちどき
火鉢の上の小さい鍋で豆腐がことこと煮えてくれる
障子切り張りしたあとがきわ立って晴れとる
洗った障子の雫を大松に立てかける
障子張りかへてきたない顔をしてゐる
障子張りかへて居る小さいナイフ一挺
朝から石塔ほる音の一心にほる音
くたびれた足がちやんと二本ある
ぱったり風が落ちた昼の銭湯に行く
思いがけもないとこに出た道の秋草
ちっとも風が無い道の郊外で児を連れ
淋しい顔した二人で道で逢って居る 放哉
如何にも静かな一日の机であった
みんながお山の冷たい水で顔洗って来る
肩のこりを掴むわが手ある曲がらせ
わが肩につかまって居る人に眼が無い
未だ明けきらぬ松原の神居ます
小さい臍が一つあった赤ン坊の腹
豚がたかく売れた話しをしてゐる満月
低い土塀から首が一つ出た
大根大きく輪切りにする
旅立つ朝の妻の顔がある竈の火 放哉
静かなる日の名も知らぬ花咲きたり
朝顔べったり咲かせて貧乏だ
一番遠くへ帰る自分が一人になってしまった
久し振りの顔がランプつけて来た
水車一つ廻らせて昔しのまんまだ
思ひ出せない顔に挨拶して居る
欠伸して昼の月見付けた
小供四五人で足音を揃へ
新聞ばかり勉強して電車に乗ってる
二人で泳ぎ出して遠く距たり
となりの藪から出て来た筍でぬかれる
遠く離れてしまった島近くなる島
蝿とり紙をふんづけた大きな足だ
疲れたこんな重たい足があった
テーブルの下で足がいたづらして居た
初夏の女の足が笑ひかける
切られた縄がだらりと地に垂れた
絹糸切ってくれた糸切歯
ポケツト探す手がなにかつかんで居た 放哉
月がさして来た窓に本がなげてある
小さい窓あけて宵月を探して居る
考へ考へ児が絵をかきつゞける
蓮の葉押しわけて出て咲いた花の朝だ
子供がはぢめてをぼえた唱歌だ
赤ン坊に邪魔されて新聞をよんで居る
昼の握りめしたべた軽いからだで歩かう
腰を下ろした石のまんまで暮れとる
屋根やが煙草を吸って居る高い屋根だ
大きな蚤を押えたひとさしゆびだ 放哉
八月のあばれ蚊を叩きつぶしてゐる頭だ
松かさ一つでも落ちて居らぬ朝は無い
お客さんにこの風を御馳走しよう
松原松のなかから可愛いゝ児が出て来た
この辺で待ち合す約束であった
今、夜あけた道自分が通る
コスモス折れたる立てヽ見る
大松腰を振って秋空立つ
二人が手をひろげて大松だききれない
少し饐えた芋を捨てる犬が喰はない 放哉
句稿(12)
層雲雑吟 尾崎放哉
町の黎明の鳩光り立ちをさまり
玄かん太陽さす埃りに訪ねて居る
切られる花を病人見てゐる
病人花活ける程になりし
寝ようとするひと間だけ月あかり
青唐辛焼いて居る白い皿一枚置き
乞食日の丸の旗の風ろしきになんでもほりこむ 乞食日の丸の旗の風ろしきもつ
浜のコスモス短かくて風に赤くて
妙によう似た口もとで挨拶してくれた
新ぶんの広告らんばかりよんでる
○以下、島のオ祭雑吟です---島ノオ察ニハ、御輿も無い御榊も無い、只、大小無数の太鼓を皆で、かついでドンどヽ叩いて、海神を驚かすのです…太鼓の大なるものは、素破らしい物があります、…神戸の楠公サンのを買って来たとか云ふ、履歴ッキのもあります…小サイのは小供が擔ぐ、東京の樽御輿のワッショイ/\と同様……なか/\、よいのが出来ませんが、マア見て下さいませ、…太鼓ハ人ガ上二乗ツテ居テ叩クノデスヨ)
柿の核子吐き出して太鼓をかつぐ
天気つゞきのお祭がすんだ島の大松
お祭のゴ馳走たべあいた顔で船に間にあってる
梨子買ひに出て柿も買って来た
卵子二つだけ買うてもどろ両方のたもと 卵子袂に一つゞゝ買うてもどる
ツイ前の石屋にもお祭が来てゐる (此句ハイケマセンカ?及第シマセンカ、呵々)
もらったお祭の赤めしたべて居るわが口動くばかり
お祭り寝てゐる赤ン坊 (此句、及第シマセンカナ?)
(お祭り赤ン坊寝てゐる)
その手がいつ迄太鼓たゝいて居るのか
茲に一人淋しい男が居った島のお祭り (此の句ハニ三日考エマシタ)
お祭にあいて海に来て居る女だ
○オ祭五日モ六日モツヅクノデス
○しかし?クチナシの花ノ「女」イいネ呵々 放
句稿(13)
層雲雑吟 尾崎放哉
びっしょり濡れた大松の幹で静かな朝だ
蝿の死骸一つ前に置いて考えて居る
蝿取紙で蚊がとれて居る
涼しうなった蝿取紙に蝿が身を投げに来る
松風小寒う浴衣二枚きてゐる
さかなの匂ひがまだ残る手よ秋風
朝の静かな気持で墨をまっすぐにすらう
ホゲ吐いてケソとへる芋腹
炭の粉眼に入れて朝から泣いてゐる
陽が出る前の山山濡れた烏をとばす 陽が出る前の濡れた烏とんでる
木槿の花と遊ぶ児よ手がかゆいぞ足がかゆいぞ
硯洗って干す木槿の花に陽ある
足袋はいて朝の庭掃けば初秋らしう
夕立からりと晴れて大きな鯖をもらった
暖簾から首の因業をつき出す
てんぐるまして児に葡萄をとらせる
ことこと小豆を煮て朝の手紙読んでゐる
米櫃に晩の首を落し込んでゐる
ひっそりさしてゐる児よいたづらしてゐるな 放哉
珍らしい客に訪はれて居るどしゃ降りの夾竹桃
ころりと横になれば蜘妹の巣が見える
時々とんぼに抜けられて涼しうなったこと
秋山海が見えるところへ腰を下ろす
握り飯の竹の皮が吹かれて居る秋山
深夜のあたゝかさを感じ小さい火鉢
たまたまお客がある小さい火鉢だ
水をいっぱい張ってから朝めしにする
口あけぬ柘榴は枝に残され
知らぬあいだを阿呆と話して居った 放哉
ぴしゃりと児を叩く音も暮れてしまった
母子で代る代るおぢぎしてお墓
嫁ツ子嫁ツ子向ふの山からとんで来た
藁屋根雨ふり足りて晩の煙りをあげる
納屋をごそごそ云はせて居たが灯して住んでる
鶏頭五六本ぬいてしまったとも見えない
朝霞豚が出て来る人が出て来る
山は今日も暮れて人住むあかりが灯る
松の葉に刺されな寝に来る雀
二階の障子はりかへて海風の家あり 放哉
壁土もちあげる土の重たさ
とうからぶらさがって居るからかさかへさねばならぬ
豆腐半丁水に浮かせたきりの台所
浴衣に足袋はいて居る庵の秋である
垣の竹に足袋干すたった一足
手拭かける釘がきまって居る
山の上は風が強い赤とんぼ
朝から四杯目の土瓶とだまりこんで居る
とうとうつまらしてしまったきせるほり出す
箸が一本みぢかくてたべとる
晩のお光りが消えてしまっただけの庵よ 放哉
蜥蜴の切れた尾がぴんぴんしてゐる太陽 蜥蜴の切れた尾がはねてゐる太陽
焼米一粒畳に落ちて居る口に入れて置く
風の格好の青い枝山から切って来た儘をさす
葉蘭の葉ずれの音よ障子しめて居る
灯の下さらさら音させ小豆を袋から出す
まっ先きに酔ってしまった穂亡がうたった
石が生きて居る話しを聞かされる石屋少し酔ってゐる
晩の少しの埃り掃き出す庵の音ある
蚊に喰はれた跡をかきかき書いてゐる
鐘がなる鐘がなる夜の風が持って歩るく 放哉
お遍路の杖が新らしくて初秋
今朝は南風の庵のしっとり雨気ある
木槿一日うなづいて居て暮れた
お遍路木槿の花をほめる杖つく
線香立てる灰を乞はれて居る
眼がわるい人で佛の線香くゆらし
しとしと雨となる今頃京都で逢って居るだろう
木魚ほんほん庵の蚊いつ迄出ることか
久しぶりに庵を出かける猫が見て居る
こっそり蚊が刺して行ったひっそり 放哉
灰に字を書いて線香が消えてしまった
淋しい松だけはやし小さい島ある
何がたのしみに生きてると問はれて居る
茸がはえぬ此の山風のこの山
起きあがった枕がへっこんで居る
長雨でどこもかも濡れて庵
雀が鳴かぬ日の庵の雨まっすぐに降る
朝から雨の海船一つ置いて居る
びっしょり石塔濡れて秋雨よろし
セルの袴でやって来たまっ黒な顔の兵隊さん (星城子来シトキ)放哉
葬式のもどりを少し濡れて来た
晩の煙りがゆっくり逃げる山里は雨
朝露の草原歩るく痩せた脛をまくる
たった一つ啼く虫地の底で啼く虫
庵をそっくり暗にあづけて出かける
鵙だな朝顔洗ふ水が冷たい
雨雲かさなりかさなり合歓の木
睡蓮夜中の池が眼をさましてゐる
青空みんな出してしまった秋山
南瓜めいめいでぷくぷくふくれて 放哉
迷って来たまんまの犬で居りけり 迷って来たまんまの犬で居る
旅に立つ人と夜の銀座を歩く
晩の燕が白い腹を雛妓に見せる
病人長くなりにけり浪音
自分の本が包まれて行く古本やの風呂敷
思ったより大きな人と初対面申してゐる
始めて逢った二人で好きになって居る
堅い軍隊パンを噛って一時をきく
となりの鶏が産んだ卵子が御馳走
たったひと晩でお別れか
(以上五句、星城子来庵ノ際)放哉
句稿(14)
※○島の明けくれ
層雲雑吟 尾崎放哉
木槿いつまでも咲いてくれる白よ一重よ
すきな海を見ながら郵便入れに行く
すきな海が荒るればわが心痛む
舟が矢のように沖へ消えてしまった
網干す炎天筋肉りうどりう
いつも海にとりかこまれて居る島人の心
山の上の芋堀りに行く朝のスツトコ被り 山の芋堀りに行くスツトコ被り
下駄のまんまざぶざぶ海には入って洗ふ
芋堀ってしまへば大根が太ってくれる
赤ン坊がほり出されたまんまで太って行く
海風へだつ一枚の障子あるきり
水汲桶の底をぬいてしまって笑った
人間並の風邪の熱を出して居るよ 人間並の風邪の熱出して居ることよ
水吹けば光る蛍草蛍にやる
雑草朝の風の中蟹が眼を出す
突っかけ草履の冷たい鼻とがらす
きつくしめすぎた鼻緒がゆびのまたにあった
鼻緒しめていさゝかのゆびの泥をはらう
こんな屋根の下から人が出て来た
朝のうちにさっさと大根の種子をまいて行ってしまった 放哉
さっさと大根の種子まいて行ってしまった
夕靄溜まらせて塩浜人居る
已に秋の山山となり机に迫り来
裏山草の風あけがたの雨ありけらし
生ぬるいビールで西陽の蝿にたかられてゐる
芋喰って生きて居るわれハ芋の化物
蜘蛛もだまって居る私もだまって居る
下り路となる海へお別れ
うたをうたって洗濯してゐると手紙で知らせて来た(れうチャン)
をそくなってから出る月も見る窓である
国勢調査の通知をよく読んでから寝てしまった 放哉
何やらふんづけた時蛙に笑はれる
蛙釣る児を見て居るお女郎だ
酒夜となる蛙等の夜となる 酒蛙等の夜となる
子供あやす顔で泣かれてしまった
巻たばこ吸ふ乞食が反り身になる
久し振りの雨の雨だれの音よ 久し振りの雨の雨だれの音
盆踊りにつかれた顔で芋堀ってゐる
雨空はりつめ昼も蚊やり線香をたく
長い釣竿一本のばす堤の風の中
障子の外からをとなはれて居るも秋 放哉
何かことこと音させて待たせてゐる
炭俵げそとへらしてこわれた火鉢抱えこんでゐる
庭先きの空逃げて来る晩の煙りさへ
少し小さい足袋を無理や理にはいてしまった
都のはやりうたうたってあめ売りに来る 都のはやりうたうたって島のあめ売り
かたづけかけた古い手紙をよんでゐる
厚い藁屋根の下のボンボン時計
すぐ死ぬくせにうるさい蝿だ
咲かねばならぬ命かな捨生えの朝顔
夜中の雨に眼覚め月に眼覚め 放哉
すっかり青田となった夕ベの虹が片足落とす
蚊帳のなかすね立てゝ居る外はまだ明るい
蚊帳のなか一人を入れ暮れ切る
昼も出て来てさす蚊よ一人者だ
昼便の手紙が無いときめて少し寝る
風が何やら耳に話して行く草枯れて山路
枯れた風の芒を折るばかり海を眼の下
漁船ちらばり昼の海動かず
焼いたばかりの枯れ草の朝の山路
釣ランプの下で親子が晩めしたべるのが見られる
海へ半分切り落とされた山の青空 放哉
一人の山路下りて来る庵の大松はなれず
瓜も茄子も山羊に喰はれてしまって窓一つあいてる
瓜盗人の山羊のあごひげ石よあたれ
山羊へラヘラと笑ふ風の尻向けたる
さかなはよう売ってしまってサツサと帰らんせ
西洋葡萄かついで来た片眼で押しうりする
島のポプラみんな大きくなり裸の児ばかり
月夜豆腐屋を探してありく
庵の藤棚藤豆一つありけり
山からうんと青い枝折って来る仏さまと二人分だよ 放哉
家家網を干しつらね夾竹桃赤かりけり
一人の机ひきよせごまの石をえる
梨子を一つあすの分に残して置かう
深々朝の海へ下ろす小さい島の根
いつも眼の前にある小さい島よ名があるのか
引き汐の島へつゞく道となれり
舟には誰も居らぬらしいあしがをぢぎして居る
三味線が上手な島の夜のとしより
たった一つの窓東にもたされて太陽
提灯襟にさすことの知恵を出して居る 放哉
たれにも逢はで来し道の秋草
汐浜南船北馬と見る夕ベもある
色が白うてエゝ娘になったぞな
きざみたばこのなかから一銭出て来た
白黒まぜこぜの畳のヘリで夏がいんだらしい
アスピリンきらきら光る呑んで寝る
あれもいっ時これもいっ時鐘撞く
大松太くて子供がのぼられぬ
朝の机ふくやひや/\経文
いとも静かなる昼の半紙買ひに行く 放哉
橋まで来てから思ひ出したことであった
郵便やが通ってそれから犬が通って浜街道
いつも暗いうちに井戸水汲み去る足音がある
今夜も星がふるやうな佛さまと寝ませう
石に腰かけて居た尻がいつ迄も冷たい
洩るのかな土瓶すましこんで居る
鶏小屋半日でみんなこわしてしまった
きせるにたばこつめる間を考えて居た
お茶がしゃんしゃんわいた音の筆をく
わが窓の秋は葉蘭二三枚の風
句稿(15)
層雲雑吟 尾崎放哉
すっかり暮れ切るまで庵の障子あけて置く 障子あけて置く海も暮れ切る
沢庵のまっ黄な色を一本さげて来てくれた
寄席を出たすき腹の小さいかげが一つ
お互に知らぬ顔をして居たまでさ
山に芋を堀りに行く犬がついて来る
満潮の島へ行かれない風吹く
縁の下から雀がひょんと出て来た
てんでに臭い物の匂ひを嗅いで見る
でこぼこの島の梨子売りつけられてゐる
あの海からとれたさかなを焼いてゐる 放哉
手が墨を逆さまにすって居った
海の青さが変る朝から庵に居る
アヅキ島らしいあのしまに名があったのか
島に居ればめづらしい支那人が物売る
あす朝満潮のときに手紙を入れに行かう
台所の障子を誰かあけそうな月あかりだ
砂いぢる児等の白砂糖も赤砂糖も暮れてしまった
笑って居るのだがうしろ向ひて居る
帽子を被るくせを忘れてしまって禿げとる
ひとの袷をもらって着て手が出足が出 放哉
夕空透かす松四五本むかしから四五本
神棚にのせて置いて忘れて居った
島の夕陽は松一本
だまりこんで居る朝から蚊がさしに来る
芋ばかり喰って月が太って来る
なんでもない字を忘れて煙草吸って居た
さっさと朝くらいうちの布団をたゝむ
電燈消してしまってから思い出したことであった
この頃鼠が静かな天井で寝る
産室の灯が洩れる襖のそとはつめたい 放哉
切り張りして居る庵の障子が痩せてゐること
幾とせの月にさらされ庵に人居る
夫婦喧嘩して居るよい月夜だ
空模様晴れてきめた顔窓から入れる
熱いお茶こぼした膝小僧いたはる
寝るだけの火鉢にまた戻って来た
ひょいと持ちあげた火鉢が軽かった
軒の雫がま遠になり風来る
浜に出て来て海風にぶつかつて居る
障子だけしめて寝る月あかりで死んだやうな 放哉
夜中ひどい風のなか半弦の月はすすむ
茸狩自分ばかりが男であった
落葉ひとしきり古帽にたまってくれる
はらりと出た落葉寝まきに着かへる
山に大きな牛追ひあげる朝靄
陽に焼けそめた海水浴の女等
畑のなかの近か道戻って来よる
潮のしぶきに濡れた顔ハンケチでふく
みんなわしが産んだ児等を集めて居る
黒雲が早い夜中の星が出たりはいったり 放哉
長雨の山山でめづらしい客がある
北を塞ぐ山の高低く秋来る
トロを押しては乗って行く草限りなし(満州)
畳を歩く雀の足音を知って居る
あすのお天気をしゃべる雀等と掃いてゐる
山の赤土ほろほろとこぼれるばかり
尻からげして長い足だ
西の空見てから寝ることにして居る
台所の団扇を握って朝がはぢまる
鶏頭少しの風でもたほれる 放哉
晴れになる風が変った葉鶏頭二た株
あらしがすっかり青空にしてしまった
窓の朝風と仲ようして居る鉢花 窓には朝風の鉢花
松の葉が暮れた地べたに突きさゝってゐた
帆柱がみえるだけの帆柱がみんな動いて居る
こゝにはいつも陽がさゝぬ蟹の穴がある
だあれも来ぬ庵のよい秋のお天気
朝の畳を掃くとぶ蜘蛛が居たよ
落葉掃きよせていっぷく
葉鶏頭の美くしさに見られる顔だ 放哉
句稿(16)
層雲雑吟 尾崎放哉
一日風吹く松よお遍路の鈴が来る
羽織を着ないで帯をきちんとして居る
羽織を着ずに居る顔に夕陽が落ちてしまった
お粥の腹を重たくして座って居る
静かなる日の藤の枯葉がよく落出したこと
長い着物をたくりあげてきて冬になる
朝赤い顔して大根をくれて行った
大根が太って来る朝々またれる
叩き落とした秋の蚊がなかない
麦がうれた道で先生を取巻いてもどる
朝湯あふれて居る硝子戸かちんとしめる
銭湯からもどる頃暗れてくれる
いつ迄もぢっとして居る雀だよ
ホキ/\朝の小菊を折って来る
芋がみんな堀られた大地の裸だ
霧に灯して浮きあがる船船
風の町のせわしい人ばかり
ハンケチを一寸たもとに入れて出る
襟巻を取った女の白い首だ 放哉
松の下掃く一厘落ちて居る
病床に居る晩の雀がもどって来る
松の風音なき日の熱出して居る
ばけつで茶椀と箸を洗っておしまひ
魚焼く金網が蜘蛛の巣にとられて居る
薬瓶からにして右枕で寝る
水にかした豆がひと晩で太った
いつ迄もある歯磨粉の袋を覗く
忘れられた頃の風呂敷包みが釘にかゝってゐる
蜜柑の皮をむいて咳いてしまった 放哉
○以下で一週間ノ病床雑吟感ジノ無クナテヌ内書イテ見マシタ
咳き入った日輪暗らむ
熱の手に晩の郵便受けとる
今朝は熱が無くて豆菊折る
寝床から首あげて見る豆菊咲き出した
お粥ふつふつ煮える音の寝床に居る
寝床から首あげる暮れかけた障子がある
熱いお茶一杯呑みたくて寝てしまう
寝床のまはりの古新ぶんばかり音たて
寝床から返事してことわる
雨のふる日もある寝床出て見る 放哉
暮れ方の音の中の熱ある
海を見る熱の眼を伏せ
熱の眼に船の帆大きく動く
海見て咳いて寝てしまう
脈を数えることを止めよう
生卵子こっくり呑んだ
掃かねば埃だらけの手紙よんで置く
熱が出て来た鼠が騒ぐ
春菊の香ひがふと通って行った
熱の眼があいて居る柱のからかさ一本 放哉
熱が出る時刻となり出て来た
たばこ吸ひ度い気持ちを考えてゐる
いつしか夜中となって居た寒い寝床だ
蝋燭一本立てに寝床から呼び起される
くらい寝床に病むからだほり込む
熱の小便をしに出る月夜
誰も病気のことたづねてくれぬ
ねむり薬の赤い包み紙をたたんで置く
胸のどこに咳が居て咳くのか
朝の机の前に座って見ればなつかし 放哉
端書かきかけて出て来た熱だ
熱の鉢巻を坊主あたまにしめる
あたまの上に氷袋が下がって居らぬ
売薬きかぬと思って呑む
夢を見せてくれる熱よ熱恋し
妻の手を感じ熱が出てゐる夜中
寝床をぬけて出た穴がある
淋しきまゝに熱さめて居り
火の無い火鉢が見えて居る寝床だ
うれしい手紙が熱の手にある 放哉
水ばかり呑んで居ても熱が出る
熱の手に持たされて居る三角な墨
朱筆を握って居る熱の朝であった
咳いては呑むやくわんの水がへる
郵便やさんから咳きこむ手紙受取る
御花の水かへて熱さめて居る
井戸水汲んで置くだけの寝床
風呂敷に豆かって来た晩から熱出してゐる
豆菊咲けりなんぼでも黄に咲く
熱の眼に黄な花の朝よろしく」
以上、病床ニテ放哉
風のなかに立ち信心申して居る 風にふかれ信心申して居る
母子暮しの小さい家であった 小さい家で母と子とゐる
藁屋根晩の煙りを静かにあげて居る
悲しいことばかり云ふ児である
淋しいから寝てしまをう 淋しい寝る本がない
山のだんだん畑を犬が走ってあがってしまった
向ふの岳の松に突っかい棒がしてある今日もしてある
塩浜行きかへりする人々と遠く座ってゐる
曇ったまんまで夕陽をかっと見せてくれた
夕陽かっと箒もって立つ 放哉
よく灯って居る蝋燭に心持ち風が出た
海が凪いだ小さい窓でよい線香くゆらす
火鉢でぐつぐつ煮えて居る朝からをんなじものだ
巡査が晩の自分の家に戻って居った
破れ障子しめ切った侭使はぬランプがある
一枚の端書受けとって寝る
淋しいこゝ迄手紙をこしてくれる
こんなに早く菊の水が無くなってゐた
薬呑むこと忘れてゐた薬瓶がある
小豆が一粒落ちて居た朝の小豆をたかう 放哉
句稿(17)
層雲雑吟 尾崎放哉
なにごとも無くて陽がうつる一枚の障子
露けさ秋草咲かんとするあまたの蕾
蝉なく山の家に客あり
竹薮に夕陽吹きつけて居る
風に吹きとばされた紙が白くて一枚
芋畑朝の人一人立てり
椅子が一つこけて居る松風ばかり
葱を洗って来て台所をぬらす
よく光るあの星見つけてから寝る
往復ハガキの半分が出て来た
薬瓶透き通って居る薬を呑む
薬瓶たもとに落して朝出る
咳をして痰を吐いて今日も暮れた
薬瓶のわが名前を朝の机に置く
瓶からごくりと呑む水薬がつめたい
火ををこしてくれる人も無い寝て居る
一日火の気も無くて暮れてしまった
月夜風ある一人咳して
佛の花をもらう朝の熱あり
熱の手に手紙受けとる 放哉
灯に遠く近くみんな寝てしまった
どこまでもつゞくつゞく蟻の行列
蟻をたくさん這はせて大松根をはる
馬の大きな腹が起きられそうにもない
窓から手を出した切りで暮れとる
渚遠く走り行くわが児の夏帽
お粥をすゝる音のふたをする お粥煮えてくる音の鍋ふた
一つ二つ蛍見てたずね来りし 一つ二つ蛍見てたづぬる家
ダリヤ手に持てば垂れる
朝学校へとんで行った風の子 放哉
はげしく小鳥になかれ昼前熱が出て居る
はげしき小鳥になかれて秋朝居る
早さとぶ小鳥見て山路を行く 早さとぶ小鳥見て山路行く
ぎょうさんな頭痛膏張った宿の女だった
雀等いちどきにゐんでしまった
蟇あすこにも一つ動けり
蟇やがて少し右に向きたり
眼の前出て居った蟇
草花たくさん咲いて児等が留守番してゐる 草花たくさん咲いて児が留守番してゐる
にぎやかにみんなが出て行った麦秋 放哉
栗むをむす湯気のなかの違者な顔だ
波音聞こえて来る日はかなしく
調法がって使ってゐる一枚の風呂敷
名も無い犬ころ等に秋草咲き
山の絶頂のお寺に犬が居った
夕陽いっぱいの旅舎で皆が草履をぬぐ
爪がかたくて切ってしまった朝寒
桐の葉が大きな田舎の町の朝を歩く
牛の一と足一と足がそのからだを支え
牛が横こ眼をした風吹く 放哉
午后の陽にまるまって居る背中もたいなし
爪切る音が薬瓶にあたった
座布団かたくなるわが尻尖る
どれも汚ない足のゆびの爪だ
雀を掴まうとしたわが手であったよ
左のゆびで煙草つめる癖を忘れてゐた
足袋から爪切る足を引っ張り出す
シャッポから豆が一つころがり出した
爪切ったゆびが十本眼の前にある 放哉 爪切ったゆびが十本ある
箸を左手に持つ児であったよ
月がまろくて児等に呼んで行かれる
墨をすってもすっても水であった夢
なんとよい夕焼の島で煙りをあげる
来る船来る船に島一つ座れり 来る船来る船に一つの島
葬式のかねがなって近よって来る
橋を渡るにも唱歌うたい連れる
朝の風雲の下火を焚きあげる
たもとのなかに紙切れも無し
秋の流れ幾つも渡りヨボの家ある 放哉
足もと灯を見せられる夜の青草
夜の青草提灯につけて来し
小さい落し物ありけり夜の青草
いつ迄も灯をかかげ見送られ青草
手と手をつなぎ夜の青草
青い月ばかりなる夜の青草
更けて送り出される夜の青草
踏切番の顔ちらと見し夜の青草
見て居るうちに消えてしまいそうな月だ
タバコの煙り雲となり朝月 放哉
障子があいた音を葱畑で聞いて居た
釣人雨晴るゝを知る
今夜のことの魚籃をしっかり腰にくゝる
毛を切られた犬の尾がかなしく動く
残忍の人の眼の色を見まじ
漬物石がころがって居た家を借りることにする
文身して見ようかと若い女の血が云ふ
若い女が小ゆびから少し血を出した
お椀を伏せたやうな乳房むくむくもり上る白雲
たゝけばなる筋肉の浴衣きる 放哉
舟は皆大松の下にかゝり
手を水になぶらせて舟静かに漕がるゝ
舟つけてタバコ買ひに行ってしまった
舟をしっかりくゝり付けて青草
ふなうた遠く茲にも聞いて居る一人
波のうねり大きく青い音をひそめ
舟からむくりとあたまあげたり
遠くへ広がって行くばかり池の漣
はや魚藍にあまる魚白し漣尽きず 放哉
句稿(18)
層雲句稿 尾崎放哉
櫓を漕ぐまねをして月夜の女
秋草のなかを濡れて来て訪はれし
家のすぐ前を汽車が通る裸で呑んでる
生れたばかりの童である秋の陽さし
障子の桟が折れて居る張ってしまった
大きなたんぼの夕湯で声かけられた
鳳仙花の実にはぢかれた長いたもとだ
鳳仙花の実をはねさせて見ても淋しい
今日も夕陽の大松が斜に出てゐる
夜の木の肌に手を添えて待ってゐる 夜の木の肌に手を添へて待つ
がらりとあけて訪はれた秋の障子である
踊り子障子にうつる夜の町の旅人とし
乞食が白いめしたべて居る石に腰かけ
高い石段をあがり切った松風ばかり
風の道白々吹かるゝ墓道
犬がをそくもどって来て寝たけはひ
縁の下一つ啼く虫ある今宵よ
鼻のさきの菊が咲き出した低い窓である
初秋の家の人等に交り新妻 放哉
ほのぼの明け行く昨夜の河広かりけり
大根ぶらさげて立つなんと大きな夕日だ
庭に水打ってしまった尻からげ下ろす
ふところ手して稲の穂にふれ行く
秋陽さす石の上背の児を下ろす 秋日さす石の上に背の子を下ろす
家うちに居て芒が枯れ行く こもり居て芒が枯れ行く
浮草とて小さい風の花咲かせ 浮草風に小さい花咲かせ
小流れ足のほてりをさますお地蔵
宿屋の庭をひとまはりして来た無花果
姿見の前も考えて歩いて来た 放哉
朝晴れ晴れした顔を合はせて居る
障子の穴から覗いても見る留守である 障子の穴から覗いて見ても留守である
風呂しきの小いさい穴が豆をこぼす
ごみを一つつまんで捨てる秋朝
菊を一株盗まれた穴に陽がさす
ごそ/\寝床の穴には入っておしまひ
どうどう火を焚く音の秋の障子
眼が覚めた寝床の上に天井が無い
青い蜜柑を朝からたくさんもらった
水がめから芋の顔がはみ出してゐる 放哉
うんと松葉を散らして夜明の松風
足のわるい人が菊を提げて来た
猫を叱る声がする昼間寝て居る
立ち寄れば墓にわがかげうつり
蟹が顔出す顔出す引潮の石垣
海風に声からして居る
青空焚きあぐる焚火大きくて一人
島の巡査となじみになった
ふところ手して忘れた事をして居た
いつ迄も赤い鶏頭で住みなれる 放哉
鏡を買って来たが見たことが無かった
あごにさわる手にひげがのびて居る
ぺたんと尻もちついて一人で起きあがる
ご馳走たべてしまった白い皿がある
今朝顔を洗はなんだこと思い出してゐる
庵を導ねると云ふハガキがとびこんだ
手紙のしまひから赤い三銭切手が出て来た
朝が奇麗になってるでせうお遍路さん
ゆびさきから血が出て居った朝だ 放哉
句稿(19)
層雲雑吟 尾崎放哉
○野菜根抄
小さい朱の硯がかはきやすくて
鍋の底の穴を大空に探す
針の穴の青空に糸を通す
から車引いてもどる浜街道
曇る一日手紙来らず
夜中の冷えた足が曲っていた
秋の雲動くひろびろ
玉葱のきつい匂ひの台所
ボロ帯しっかりしめて出かける
いつ迄も若い気で銀杏落葉はく
山の蜜柑たべあいていんでしまった
赤いインキが手についた朝
べンチから歩き出した者がある
ペンサキ一本買うてもどる
冬空のお地蔵さんに参る
一人児として連れらる
塩からい井戸水で冬になった
さんざん叱られていんだ
夕陽の山は淋しいな 放哉
死んだ真似した虫が歩き出した
入れものが無い両手で受ける
いっぱいの水をいたゞく
風の吹く方へ歩く草原
寝られぬ夜中の布団動かしてゐる
児に赤い足袋はかせ連れて出る
動物園からつかれて出た
朝月嵐となる
秋山広い道に出る
たくさん児を連れてブラ/\行く 放哉
いつも草履の足音が無い
水にうつるわが顔にひげがのびとる
いつもしめてある門の前を通る
絵を見て出る寒い風だ
青空のなかからふり来るもの
口あけぬ蜆淋しや 口あけぬ蜆死んでゐる
たしかに見た顔と船に乗った
風吹けば少しある海光る
どこの屋根も冬になっとる
小さい帆をあげて暮れる 放哉
障子が一枚ふうわりたほれた
又風になる小さい窓をしめる
背が高い西洋人と出逢った
注射する静脈ふくらせる
屋根にあがった児が大声あげとる
葉のなかうれた蜜柑をさがす
あの足音がやって来た
咳をしても一人
番小屋がもえてしまっただけさ
汽車が走る山火事 放哉
墓参りのついでに寄って居る
自動車の砂煙りに歩き出した
さかな一疋釣れたばかりの水面
夕陽となり釣れ出す
とっぷり雨の夜となる
一番高い山から陽が出る
秋山半分に切られた
電柱どこまでも刈田
日の出合掌している葱畑
のびて来るひげが冷たい 放哉
怪我人運び去られた日輪
白々明けて来る生きて居った
ちっともへらぬ腹を山にもって来た
一日晴れ曇り風
木の実落ちては池に沈む
冬山人があがって居る
暗らい台所でたべとる
障子つぎ張りつぎ張りして雪来る
猫の大きな顔が窓から消えた
白帆人無きさま 放哉
どこへ行ってしまったのか日曜の小供
朝々汲み代へて置くわがバケツの水一杯
唐辛しもらって昼めしにする
傷口しみしじみとわが血湧き出す
たのまれたかなしい手紙書いてあげる
どっかで猫が鳴いとる
大きな柳の葉が枯れ出した
土を運んで汗出す
粉炭掃きよせて置く土間のすみ
饅頭がまだ一つあった 放哉
女連れに道をきかれた
夜の藁屋根から三味線がもれる
庫裡の灯一つの暗らさになれ
めくらが空見てうたふ
石佛の冷たい顔で休む
静かに撥が置かれた畳
うまい茶が出た茶わんを手にのせる
日暮れの畳を掃く
写真のなかの大きな犬だ
犬も入れて残らず写す 放哉
大きな切り株に腰を下ろす
奇れいな砂のなか蜆が居る
埃をいっぱいためて客と居る
くりくりよく太った児がようころぶ
夜の波音のなかをもどる
風音の障子あけられず
いつも此の草山の高さに来る
山風下ろし来た一日の終り
砂糖なめた児が叱られた
波音ころがして蜜柑山うれとる 放哉
ページトップ
|