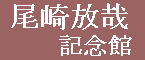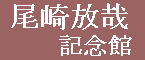[句稿集1へ] [句稿集1へ]
句稿(20)
層雲雑吟 尾崎放哉
風が落ちた顔を窓から出す
はたりと風が落ちた障子たて切って居る
かっと夕陽の風が落ちた障子
風が落ちた夜のあつい湯を呑む
短かい羽織きてちょこなんと家ぬち居りけり
風が落ちた夕べ訪はれて居る
風が落ちた晩の大根ぬいて来る
風音の夜中の柱にもたれ
風音のなかに寝る庵無し
大風のなかの手紙が来た
海を見に山に登る一人にして
少し見える海で鶏頭枯れ行く
船の笛を聞いておわかれにする
菊枯れ尽したる海少し見ゆ
朝の頬かむりして出るすゝき光らせ
葱畑のなかいとしき妻に声かけ
小供遊ばす蟹がたくさん居ること
石垣に夕汐たヽへ家深く灯せり
陽の入る山のなかから出て来た
海の青さのたのしみ尽きず 放哉
遠足の美くしき野の流れをこえ
鎌一挺腰にさして朝の山にはいる
秋雨の家を出で戻る道ひとすぢ
赤ン坊たらひの湯気を立てゝ泣いとる
朝の湖のさゝなみたち旅たち
いっしょに大根ぬきに行かう
朝から一日戻らぬ雀だ
冷たい手で手を握られた
雑誌をぱらりとあけた朝
海行く幾く日海のなかのわれ 放哉
落葉水に流れ去る風の日つゞく
果物たくさん買うて来た月夜だ
果物たべて話す灯の下ナイフ光らせ
駅前の果物屋が朝の戸をあけた
山の池の小さき魚泳げり
小供等がよってお祭の提灯ともす
朝霧流るゝ湖の遠く水見え
薮に沿ひ行く道の大きな家の門がある
流れに沿ひ一日歩いてとまる 流れに沿うて歩いてとまる
風にたほれた藤の枯棚起す力無し 放哉
海苔そだの風雪となる舟に人居る
障子しめ切って足に灸すえて居る
一日雨音しっとり咳をして居る
朝早き秋の灯に旅立ちて来し
茶わんのかけらがいつも見えて居る流れ
一枚のわが畑案山子立てるべし
萩の花咲く寺を覗いて行く半日
夕ベそば畑の石ころを捨てる
児の小さい手に椎の実拾はれ
たれも畑に居らぬ見渡す 放哉
障子の外は雀等のよい天気
客が遠方にいんでしまった朝だよ雀
今朝は雀が大勢で来てくれた
雀風に吹かれて並んで居る
いつ迄も動かぬ船を見て居った
晩の白雲かさなりかさなり帆柱
夜中の大きな音が鼠であった
今朝俄かに冬の山となり
あられいっ時の青空
風吹けば鳴るわが障子
きっとうまいぞ泥だらけの大根
冷めたさ握って居た手のひら
手のひらにゆびで字を書いて教へる
旅からもどって来た人に灯りを見せる
ひと晩とまったきりで船でいんでしまった
山から下りて風ひいてしまった
茶わんの湯気が朝の顔にかゝる
いつも六畳じきのたゝみだ
蚊帳の吊り手が動いて居る冬らし
今日で三日の雨の大松立てり 放哉
乞食が寝て居る昼間見て通る
小雨の波打際をゆっくり歩く
吸がらポンとはたいてゐんだ
草原牛が寝て居った
硯を洗って書く
東京に来て夜の火事を見に出る
立ン坊朝の寒いかげくっきり持つ
一銭もってかけ出した
とんぼの尾をつまみそこねた
赤とんぼ大勢でみんな小さいな 放哉
一日曇る日の花とて無し
曇り日の机窓によせてある
大きな栗を一つたもとから出してくれた
めくらの女に秋陽いっぱい流れ
だぶ/\川水呑んで行った牛
消えかけた榾火に大きな足出して寝てゐる
風邪声で何か叱って居る
一つ花咲き色色風吹く
垣をしっかりなほして寒うなった
朝の一本の柱を拭く 放哉
坂道牛が辷った大きな足跡
いつの間に出たのか一つ白雲
船の窓ことりとあいて小さい児顔出す
かたわの児は暗い部屋に居るらしい
晩のよごれた足を拭いてあがる
陽がさゝぬ庭の人住めり
冷え切った握り飯のなかの梅干
一日雨ふる庭の水流れ去る
どの女が鬼灯ならすのか
藁屋根低く煙りあげる黒い口もつ 放哉
句稿(21)
層雲雑吟 尾崎放哉
葱積んで行く舟の女漕ぎけり
青い葱ばかり島は秋雨
葱きざむ朝は葱がしむ眼の泣かるゝ
蜻蛉流るゝ風とて咲く花
のびあがって見る海が広々見える
腰を下ろす痛い石ころがある
水を出れば直ぐに咲く花
水の上風吹き素足である
学校卒業した顔でやって来た
見て居れば這ひ出した寒い虫よ
コレ丈ケ句作ヲタメテ居タ処---二十六日
北朗来り、ソレヨリ、温泉気分ニナリ、両人共、一句モ出来ズ候---今日三十日、「北朗」丸亀二去ル アトデ、手紙類ヲ整理シ見ルニ、私ノ「句稿」---鉛筆二テ、チョイ/\句ノ上二穴ヲアケ居り候---キタナクナツテ「業腹」故、---此憶!三送り申し候---乞御許 三十日放
生れ出た虫よ風ある大地
木の葉まひ上りどんどん暮れる
くっきり夜の戸の灯が洩れ
胡座かいてゐる島の家の水兵さん
電柱斜に打ち込んである冬田
まっ赤になったほゝづきが舌でならされる
星根に秋草の花をのせ枯してゐる…
麦がすっかり蒔かれた庵のぐるりは 麦がすっかり蒔かれた庵のぐるり
麦をすっかり蒔いて小便してゐる
もづがなく朝霧とぶ 放哉
入梅しんみり夕陽の小家いつも見て暮れる
舟が一つも居らぬ日よ夕陽よ入梅
夕陽大松を越え山を越え静かに行く
昼は小供が番をしてる島の雑貨屋
はるかなる畑のもみぢ一本明るくて住む
ぢっと見て居る堤の帆が動いて居る
さんざん淋しい目をして来た顔が円るいとさ
さかな焼く晩の煙りの家が押し会ひ
昼月風少しある一人なりけり
墓地からもどって来ても一人 放哉
「亥ノ子」ノ日、新十一月二十三日、作、---コレカラ愈、寒クナツテ参ルソヲデス「亥ノ子」ナンナ言葉ハ久シ振リニキゝマシタヨ、難有/\
章魚をもらった朝まっ赤に煮あげた
ころがった林檎が落ち付いた灯のかげある
鰌きゆうきゆうなかせて割いとる
船が錨下ろす迄たばこ吸って居た
風呂敷包み一つもって艀にのる
艀こぼれるように人乗せて来る
をくれて一人艀に乗った人で漕ぎ出す
島は紅葉を照らし舟から上る
艀人を盛りあげ小雨のなか 放哉
拭くあとから猫が泥足つけてくれる
猫の足跡に笑はれて居る
どっか近所に飼はれて居るらしい片眼の猫だ
なに気なく振りかへる猫が歩いて居た
山はなだらかに入江の青さに入り
畳の上の小さい紙切れに風ある
まっ黒い畳に机が一つ引っ付いてゐる
火が出来た朝霧吹きこむ窓
直ぐ灰になる火を大事にして夜
静かなる煙あげ大きな藁屋根 放哉
句稿(22)
層雲雑吟 尾崎放哉
小さい窓から首突き出して晩秋
ひどい風だどこ迄も青空
お遍路鈴音こぼし秋草の道
風なくて居る庵の上鶯なくらし
犬に覗かれた低い窓である
海風のなかで芋堀る
砂に雨落ちはぢめ浪音はなく
浜の雨となり頬かむりしてもどる
出べその児も居てあつい浜砂
炭俵に突っ込むたびの黒い手だ
船の灯一つ安らかな窓あけて居る
家々夕ベの煙りあげ旅人行くなり
禿げあたまを蝿に好かれて居る
子に手を引かれ母親眼が無い
霧雨の山に朝の煙りかゝり
青田ひろ/\冷豆腐たべて出る
落葉掃く方に夕風少しある
落葉掃きよせて暮れてしまった
すっかり晴れ切った空の山山並び
落葉焚きつけては入ってしまった 放哉
此ノ頃、「乳房」トカ、「髪」トカ「女」トカ三放哉此頃女ガ恋しくなったかと冷笑スル人ガ有リマスガ、全く左二非ズ、此頃、新ぶんノ新らしい和歌を見て、ヒントを得て和歌なんか、アマイもんだ、俳句ノ方が今少し濃艶ダゾど、「試み」て見たワケデス、モノになりますかな、幸、「乳房」ト「髪」トハ十一月号二採ツテモラツタケレ共…
恋心四十にして穂芒
女の白い手が眼の前で消えた
女の足が早くて穂芒
美くしい女で菅笠をかむり
太った女がたら/\汗ふくそばに居った
ハンケチ忘れて行った女であった」
小さい手足を動かして眼を覚ました
帽子かぶって出るくせの宵祭
島の人等に交り自分一人帽子かぶって居った
水がめのまろさころがし行く 放哉
なんと丸い月が出たよ窓
火事がすぐ消えてしまった宵だ
町内の顔役に候蝙蝠
遠くから例の小供の納豆売が来るよ
落葉焚きあげた坊主頭だ
小坊主二ツ寄って落葉焚いとる
羽織袴で墓場の夕陽から出る
ゆうべ杓の底がぬけた今朝になって居た ゆうべ底がぬけた柄杓で朝
猫の足音がしないのが淋しい 放哉
ふと顔見合せて妻と居った
女よ女よ年とるな
たもとを短かく切りつめた我が妻とし
旅からもどった妻の顔とぶつかった
嬉しさが押え切れないで女よ
夫婦で見送られて一人であったは
さんざん叱った揚句の妻よ
みんな若い人だちに西瓜が切られる
風につぶされた家がいつ迄もある
駄菓子が好きな坊主を笑ひ給へ 放哉
海が荒れる日の漁師が酔って居る
火の無い火鉢に手をかざし
ひどい風の中咲く花白し
藁灰焚き置き朝の裏口
がらり障子をあけた小供であった
立話して居てめしを焦がした
朝の一枚の障子をあける海風
小ざかな生きて居る夕河岸
生きて居る蟹を買ってしまった
お賽銭集めてハガキ買ひに出る 放哉
縁かわあたゝかくて居る木の葉が一枚とんで来た
犬がなく山の村の灯が見える
くらまぎれから犬が出て来た
落葉掃いて居る犬に嗅がれる
島のお天気は静かなる電線
裏の小供と仲よくなって菊が咲いて
佛の灯が消えて居るのを知らずに居た
石油買ってもどるちょい/\紅葉しだした
堤の上から昼の帆柱がふらふら動いてゐる
あついお茶を呑んで落葉掃きに出る 放哉
一日障子を風にならして読んで居る
障子のつぎ張りも松風の景色
茶わんが白くてだまって台所暮れとる
山に登る山の畑の牛なく
いつも洗濯してる女で色白で
柿の木一本赤くして洗濯してゐる
落葉掃きたくない晩もある
草履が古くなって来た落葉はく草覆
いつも草覆をはいて暮らしてゐる
ぬれた草覆をかはかすよい秋晴れだ 放哉
いつ迄も曲ってゐる火ばしで寒いな
犬が小供をうるさがって居る
紅葉まっ赤な急流の舟を捨てる
流れがゆっくりして来た平かな石ある
温泉になんべんも出てははいっては青い急流
夕陽のなかの土瓶が一つ
夕陽海に親しみ暮れる
肩がこったな松の葉を掃く
爪を切ってしまったカッと夕陽 放哉
句稿(23)
層雲雑吟 尾崎放哉
青空の下で話して別れた
草刈りあたまをあげた知らず
化粧が早い妻と連れ立つ散歩
つい銀座に来てしまった
汽笛海へならし空へならし
風落ちしより落つる松の葉 風凪いでより落つる松の葉
障子の穴から太い手が出た夜話でもどる
もどる時の土間の下駄が見えない
山の上の人が何か話して居る
眇眼で見られて居るやうだ
雪の頭巾の眼を知っとる 雪の頭巾の眼を知ってる
神社の雪晴れの音をきく
一人二人の夜の雪道となり
小さい児が雪の小さい道つける
小さな島々雪を残し
はるかなる山の雪見て過ごし一と夏
雪道あけるあけぬの喧嘩
雪の町はづれとなりかなしく
雪の家を探しあてた
夜通し雪の街燈 放哉
霜夜の遠くの半鐘
暮れる雪ふる酒席となり
満天雪を散らしはぢむ
青空雲散らし街燈の群集
雪の下駄わが門に叩いてはいる
向うから来る人と近くなる雪道
湯気吹く雪夜の銕瓶
青空半天の雪を落とし来る
今夜は雪だと風呂での話し
雪道遥かなる原の小さい太陽 放哉
雪かく朝の小さい手もかりる
雪晴れ舟動く
雪の中の庭石堀り出す
足もと降る雪の提灯
松山雪風鳴らしはぢむ
雪道銭を落とす
雪に杖たてる深し
雪のひと間を出でず
帽子の雪を座敷迄持って来た
南天うつむかして夜の雪やむ 放哉
雪道まっすぐに下りる渡船場
たれも居らぬよ雪の渡船場
残雪に雨ふる
雪の藁屋根祝ひごとある
暮れニもどる雪あかり
池一つ雪をためず
外は雪となりしお芝居
雪に面形つける遊びを知ってる
雪の上焚火捨てゝある
夜の雪ふる音を見る 放哉
雪晴れのたんぼへ障子をあける
どこ迄も雪の一本道
雪の障子をあけた美くしい児だ
雪のお寺に美くしい児が居た
雪丸げ重たくなって捨てる
町へ入れば雪無し
マツ赤な頬だまの雪晴れ
雪の湖から小海老がたくさんとれる
雪道奇麗な橋があった
温泉の町の雪深し
寒鮒みんな子をいっぱい持って 放哉
船の横腹に石炭つめこむ冬朝
月の光り母子でもどる
冬野大きな穴ある
立ち話しして居るわれ等のかげくもる
日曜秋晴れの道縦横
月の光り寝た家にもどる
あられがころがる牛の背中
提灯もどしに行く落葉ふる道
平かなる石の上風吹き出で
あかつきの風弱り朝月 放哉
自分ばかりの道の冬の石橋 自分が通ったゞけの冬ざれの石橋
いつしか雲が消えて居た窓の机
縁日の坂道菊をかつぎ
焚火のうしろの暗さ
風の落ちぎわの犬の顔
霜朝一寸窓をあけた女
山宿朝霧流れあつい飯たべる
遠くの高い山へつゞく此の道
枯草たっぷりと冬陽ある
案山子の一本足が出て来た 放哉
灯を消して寝るわが寝床
雲吹き散らす風の雲のさま
はらりと落葉つながれた猿が見てゐる
玄関久しい菊の鉢持ち去る
豚が一疋逃げ出した裸か木
内庭の高い木が一本葉を落とす
門口に出て見るあすの天気
鶏頭引きぬく土少しついて来た
藪のなかの紅葉見てたづねる
太い桐の幹だけ見えて待たされて居る 放哉
遠くの渚に舟一つありけり
わが顔のまはり灯を置き縁日商人
杭を打ち込む音があとから聞こへる
小供が来る犬が来る町中のあき地
星のなかのなぢみがある星
紅葉あかるく小石を拾ふ
ぎしぎし荷をしわらせて来た雪のさかなや
さかなやどんぶりからざく/\銭出す
寒き日となりし生花かへる
今日の大地の仕事を終る 放哉
句稿(24)
層雲雑吟 尾崎放哉
※○寒空
名も無き冬の山山並び
とっぷり暮れて雨を落とす
しゃがめば顔に近きだりやの花
日曜はをそい朝めし
この木の花を見た事がない
大根ぬきに行く畑山にある
麦まいてしまひ風吹く日ばかり
枯枝ぽき/\折って焚く
低い山なれど海風強く
冬風に吹かれ働らきつめる
うしろから吹く風海風
人力のからをひいて戻るにあふ冬田
一日砂利運んで居る
雪あかり一日の小窓
もどさねばならぬ首巻が釘にかゝってる
池の氷に穴をあけて去る
山茶花が咲いたのでよい庭だ
少し開きかけた椿をもらった
冬の港にま白い蒸汽が来た
温泉の町を歩く朝の白雲 放哉
その夜の池が氷って居た
やどかり畳に置いて見てゐる
ダリヤ畑の陽によって来し
雀の軒を並べ郊外にすむ
公孫樹が散る寺から使ひが来た
暮れてしまった生垣なほしてゐる
山路花あればつむ小供
町を流るゝ大河の夜更け
むかし此の石落ちて来しより冬田 放哉
右手のゆびが下手くそな煙草をつめる
一人呑む夜のお茶あつし
戻って来て土瓶の腹に手をあてる
軒を並べて昼の客引く家々寝たり
やっと間にあった汽車が居てくれた
今朝の霜濃し先生として出かける 今朝の霜濃し先生として行く
板の間の霰音たてゝ消えたり
たった一本の野の木を見上げる
煙りをどんどん青空へあげ消えた畑
冬空少しあかるくなりぼんやり居る 放哉
たらなくなった葱をぬきに出る月夜
となりにも雨の葱畑
寒い手がたばこをつまむ
咳して出る寒ン空
長い橋のまんなかに来て休む
痩せた尻が座布団に突きさヽる
右の手の爪だけ切って忘れて居た
土瓶わいて来た麦のよい匂ひを入れる
寝て居る顔に夜の壁土落とす
海風吸ひあき秋 放哉
つるりと辷った白足袋
古畳どす/\歩く
足袋ぬぐ赤い鼻緒のあと
風が落ちた監獄
冷え切った右手いとほし
火鉢の灰をへらす
蕗のとう見つけたある朝
故郷の道をまちがへず
医者の大きな門が無くなってる
一寸窓をあけた寒ン空 放哉
朝の大波となり寒ン空
破れ切った障子に手を突っ込む
お医者と考えとる
薬はきかぬときめ水仙が咲いたは
お医者は釣りに行って居た
くづ湯がうまい風の無い夜
風が無い夜の粉炭がをこる
風が落ちた草履をはく
残雪の顔を剃る
くるりと剃ってしまった寒ン空 放哉
用事の有りそうな犬が歩いてゐる
濡れて来た犬と眼をあはす
夜中のすき腹に焼餅一つ入れる
やんちゃは隣りの医者の児だ
うんと足をのばして壁にさはる
女今日は犬を連れて来ない
電気がついても戻って来ない
赤ン坊あまりよく寝る雪晴れ
胃袋の有るところも知らぬ女だ
遊びつかれた灯だ 放哉
三銭切手も張ってしまって寝る
たもとについた灰を知らずに居た
夜中の痩せた骨にさわって見る
鼠が噛る夜のよい音だ
庵は静けさの小さい鼠大きな鼠
よい気持の腹が太ってゐた
机の下が奇麗な朝だ
夜なべが始まる河音
大松ひょいと風落ちた幹 放哉
雨のお医者に手紙もたせてやる
小料理屋には入る銭ある夕べ
古新ぶんの音を踏んで起きる
下手くそな医者菊咲かせたり
爪のあかを見もしない
庵の春は書きとばす五色短冊
畳の焼け焦げがいっつも二つだ
今日がはぢまる机がまっ四角だ
乏しうなった半紙折って居る
よい処へ乞食が来た 放哉
句稿(25)
層雲雑吟 尾崎放哉
とび出しそうな大根の出来だ
藤だな藤の骨からまぜて冬空
はだかの背なから寝た児をはぎとる
寝てしまった児を背中で渡す
風が落ちた庵をぶらりと出る
をんなじ事を云っては泣いとる
晩の葱四五本洗ひあげて足りる
暗さ晩になっとる
寝る前の帯をたたむ
かげのやうな気持が歩く
今朝掃いた松葉は煙にしてしまった
お茶が煮える松葉の白い煙り
星がきらきらする夕べの煙り
山裾静かなる雨の煙りあり
バーのあかるい灯で落ち合った
食パンが無い島は芋喰ふ
遠くても海辺をもどる
いつ見ても咲きかけて居る菊だ
この山の水をたゝへ一軒家とし
宵月の顔うすうす見ては話す
まっすぐに降る小雨はうれし 放哉
雨萩に降りて流れ
一本の洗濯竿の月夜
わが雨に濡れてつわ蕗
夜の青草にふる雨音知っとる
雨夜の灯をかぞへる
やっぱり雨であった水馬
雨の電燈が来た
犬が濡れもどる垣の穴ある
寒なぎの船帆を下ろし帆柱 寒なぎの帆を下ろし帆柱
冬雨あかるい大きな柳が一本 放哉
枯れ草ぬかないで冬を越そう
奥から奥から山が顔出す
長いひさしの夕空が見にくい
眼玉菊足もとで咲く
小さい児が夜中一人でいんだ
浜には誰も居らぬ風吹き
糠雨となり居りし知らず
雨の夜の仕事がたくさんある
雨の窓で芸者はうたひ
朝方の雨を知らなんだ 放哉
一日歩いて来た山道の残雪もあった
山の草原で木の実をわける
いつ迄も立って居る畑の男
夕陽の山近し
留守番に来て居る夕陽の障子
ぬけ路次の旭日さすごみため
冬咲き残る花は黄にして
梨子のたな低く宵月
初霜旅の朝起き出でたり
大霜朝月ある 放哉
頬杖ついた窓さきさるまた海へ吹かれる
草履ぺたぺた晩の酒買ひに来る
浜に出て行った人が中々もどらぬ
ふところ手出して火種ほじくる
とても深い谷で葉をふらし
いたちがかくれた早いこと
いつ折ったのか本のぺージ
状袋が一枚も無いあすにしよう
山からあがる陽が海から出だした
月夜歩く足駄の太い歯だ 放哉
また風が出かけたばけつに一杯くんで来る
また風だ大松の下の庵
また風の障子がしゃべり出す
また風だよ裏のお婆さん
板塀ひっくりかへした夜中の風が笑ふ
水仙が炭俵の上に置いてあった
庵の障子あけて小ざかな買ってる
握りめしを落した根上り松がある
寝てもさめても吹いとる
師走の木魚たゝいて居る 放哉
まだ咲いて居る佛の花を捨てる
禿山夕陽の大松をさゝげ
大風の夜の蜜柑の種子を呑んでしまった
三度三度呑む風の丸薬
糊がかたくてつかない
フト大きな手のひらであった
風の夜の麦粉二人でたべ
さした事が無いからかさ一本
毎朝風の墓石ならべり
遠方のわが下駄に乗ってもどる下宿屋 放哉
松かさそっくり火になった冬朝 松かさそっくり火になった
小供と落葉焚きあげる昼すぎ
小供と二人山の上でうたふ
黒い板塀の切戸があいた柘榴
柘榴口あけ皆が口あけ
柘榴佛に供へられ口をあけず
色街の灯の泥川泥動く
橋に来て下駄の音みだれ提灯
銀行から出て自転車かけらす
友の顔が居る銀行の窓口 放哉
また風音のねむり薬を呑み
あすは元日のお粥の残りがある
元日いつもの風吹き
元日の箸を山で揃へ折って来る
とっくに明けて居る元日起きて来て座る
正月休みの旅の会社員たちよ
元日の朝の行火あたゝめる
元日の泥棒猫叱りとばす
元日の草履ぬぎ揃へ
風よ俗を呼んで居るな風よ 放哉
句稿(26)
層雲雑吟 尾崎放哉
暗くなって畳や片付けて居る
青空風吹きつのらせ
風吹きくたびれて居る青草
風音の布団にもぐり込む
郊外高い家建ちたり
今朝の太陽と話す
きたない畳によい冬陽さしこむ
いつも提灯張ってるお爺さん
机の足が一本短かい
ゆっくり暮れて行く籐椅子 放哉
群集のなかですぐ見付かった
ストンストン大根輪切りにする暗い手元
障子あいた音が泥大根置いていった
杉並木のまんなかを歩く
葬式のあとから来て路次に曲る
またあの東西屋にあっただまって行く
たった一人で活動館から出て来た
田舎の電気がついたり消えたりして寝る
銭湯出て電車道突っ切る
わが背中もたせる柱にえらまれ 放哉
犬のお椀に飯が残って居る
更けて行く山の一つ灯消されず
鯊釣船を湯女の美くしい手で教えらる
病人ながらへて寒うなりけり
かけ出した児が蜻蛉見つけた
曼珠沙華がみんな踏み折ってある
柳散る陽の大地のしま目
眼の前糸瓜ぶらさがってゐる座敷をかりた
朝顔嵐のなかでも咲く
鶏頭たくさん枯らして住む 放哉
柳散る井戸に蓋がしてある
ひそかに散る柳眼が知って居た
野に向けどんどん風呂たく
噴水風が強い公園に来た
噴水力のかぎりを登りつめる
糸瓜たくさんぶらさげていつも寝てゐる
児に乳呑ませて居る夜店の女だ
どこまでも土塀について曲るポスト
お盆の芋の湯気がたゝなくなった
鶏毛を散らし散らし蹴合ひ 放哉
雨の高下駄久しぶりにはきたり
歯を入れかへた下駄で歩く雪よし
雪の素足でもどって来た
つま皮新らしく白足袋を入れる
松たれさがる今し汐ひけり
妻の下駄に足を入れて見る
小さな帆かけ舟が見えなくなった
春菊の花咲く春菊の花ばかり
嵐の松かさ叩きつけられて寝て居る
松かさたくさん土間にたまった 放哉
嵐の犬の子一疋も居らぬ
青空ポツンとひたいにあたったもの
講談をよむ嵐の炬燵
白砂糖こぼした嵐の夜
はや起きて居る宿の小娘
女よ新らしい下駄を泥にした
枯草ぬく根を遠方に持つ
人肉の味の柘榴むさぼる夜の女で
嵐でたほれた家のとなりの台所だ 放哉
嵐が落ちた夜の白湯を呑んでゐる
嵐が落ちた夜のなんにも無い机
嵐が落ちた障子あける遠方が見える
嵐が落ちた晩のお白粉つけてる
人の噂さして酒呑んで居る
カチ/\になって居る蛙の死核だ
手をついた蛙の腹に臍が無い
山の池晴れ蛙勇躍す
ゐもり冷やかな赤さひるがへす
蛙蛙にとび乗る 放哉
庵は青葉の昼の雨蛙なきて
雪凍てた夜の梟来てなく
梟なく夜の乳房与へる
熱い風呂に雪をうめる
赤ン坊行水させる雪の晴れ間
児等が登る風が落ちた松の木
風が落ちた板塀をなほす
風が落ちてしまった庭石
寝た児を炬燵に置いて来る
障子あけて見た物音無し 放哉
雨の藁屋根の下の何年ぶりだらう
話す事も無くてやって来た
嫁入りのお供が山みち酔ってもどる
買うた状袋が上等すぎた
原稿紙を売ってる家が町ぢうにない
師走の青草をふむ
郊外の電車に乗りかへた
となり合せに古く住みて木こり
顔から火が出たと女が云ふ
あの星を見付けて安心した 放哉
墓地の上は星ばかり
友の絵を壁に張りて師走
師走の島は松の木ばかり
犬がこっそりちんばをひいてもどった
咳の薬りがちっともきかない師走
めくらが兎の夫婦を飼ふて居る
小さい手から蜜柑をくれた
冬雨来たらしい音の枯草
月を見上あげただけの心もち
山みち二つに分れて細ぼそ 放哉
句稿(27)
層雲雑吟 尾崎放哉
もらった餅を数えて居る元日
松の実を破(ワ)る音ばかり元日
海がなんぼでも見える今年の元日
お寺が賑かな日の烈風
一日庵の障子をならし人来ず
初旅の汽車で買った弁当
松の内のバスケツトーつで旅立つ
吹けばとんでしまった煙草の灰
石塔ほる音の年の暮迫り来
夕ベ風落ち草少しみだれ
たゞに流るヽ大河橋かゝる
秋の港の船は皆灯し
美くしい小鳥よ山路かくれし
夕ベのさかな焼くとなり同志
山の温泉の山に見あき
今日も夕陽となり卵子一つ吸ふ
今日も夕陽となり泣いてる児ども
こどもの赤い鉛筆で絵をかいてやる
わがかげ動く夜となりて座る
いつ迄も馴染が出来ない温泉の町 放哉
小さいわが庭の中の冬陽が動く
海から拾って来た石だよ潮騒
鉄砲光って居る深雪
何か居り秋の樹の葉を散らす
遠くの船は動かず
風のあとの松原の砂のでこぼこ
浜砂かついでもどる風呂敷が重たうなった
林檎の籠の到来物が置かれ灯の下
えりまきぐるぐる巻にした眼だ
あられたまる間を見て居る 放哉
内庭の空見上げては本読む
霜濃し水汲んでは入ってしまった
痩せた手首をひら/\動かす
奇れいなあたまを寄せて村の娘たち
角力とりと峠茶屋で落ち合った秋だ
太い桐の木の下草無し
芒光る野の若き心一つ
うす霜の朝背中二寒く
労働者らしく夜霧にかくれ
並んで通れぬ野の橋に来た 放哉
向ひ山陽照りてくらき窓もつ
空を見る事が好きな妻であった
小供は小供同志のお祭
松ばかりの大寺の冬
水仙縁の陽に出して銭湯に行く
小さい月夜をもどる寒さ
藪を曲れば冬の大河
一人でそば刈ってしまった
畑から暮れてもどる百姓
灰の中の釘が曲って出て来る 放哉
お墓のばけつ幾つもあづけられてる
柱の水仙が咲いた咲いた咲いた
児が出来た話しをきゝ大根煮てゐる
かた炭一俵もらった寒の入りよ来い
くもれる空動く池ありと云ふ
池をひとまはりしてかるきつかれ
妻がシヤがんでる柳已に散る葉ある
カフエーには入らうか夕陽
暮れかヽる旅の山かなしく
はるかに呼べど冬野聞こえず 放哉
もどって来た児等がチヤブ台かつぎ出す
猫の首ぶらさげた格好
猫の眼がきらひだ
秋山よき家あり人住まぬ
足がだまっては入って居た水たまり
大河流るゝよ海へ遠く
灯の街になった東京に汽車がはいる
大きな陽を落とし片舟
庭石雀が一寸下りて見た
大きな石がある風の野 放哉
こはれた火鉢でも元日の餅がやける こはれた火鉢で元日の餅がやける
粉炭はねるなよこわれた火鉢
手のひらあければ淋しや
死ぬ迄左に置く癖のこわれた火鉢
馬がをどれば馬車がをどる冬野
硝子窓に呼吸で書いた絵が消えた
石ころ幾つも海へ投げあきてもどる
砂山越えし人永久に見えず
ぶるさとのやっぱり小さい馬だ
釘の着物が落ちた音だ 放哉
寺の大蘇鉄いそいで見て出る星
踏みつけられた朽葉が氷りついた
すくすく桐の木太らせ百姓
すぐ灰になる一と抱への松の葉
いぶるものつまみ出す蜜柑の皮
落葉火になって飛ぼうとする
掃きよせた落葉風に散らされ
二三日煮たきせぬ小さい台所
向ふの山に陽のあるうちを急ぐ
枯れはてた野山かな人住む 放哉
落葉つつき出しかけひの水通る
坂道ころがり落ちて来た児よ落葉
夜の池水はま黒く
枯れ草に陽あたり牛喰む
枯れ木の中の人では無かりし
冬川せっせと洗濯しとる 冬川せっせと洗濯してゐる
渚残されし藻草つかんでかぐ
藁すべ一本落ちとる
麦藁吹いて遊ぶよ盲目の児
青い生垣に沿ひ行き気晴れ 放哉
句稿(28)
層雲雑吟 尾崎放哉
○佛とわたくし
粉炭ほこほこ顔一つあぶって寝る
夜話しが出て来る煙管のがん首
夜中の漬物石が重たい
薬を呑んでも呑んでも痩せとる
いちばんこれが近か道だ
交番に巡査が居らぬ
古畳売り物に出してる
もらった手拭に小さい役者の紋があった
かけた盃ばかりだ
大きな門の表札が無い
落葉かさこそ夜となり
凍て切った一本道を詣る
はやり唄うたって児をそだてる
郊外寒い家建ち
女世帯の奇麗にしてある
朝の水仙に水さしこぼし
今日も夕陽となって座って居る
いつも人が居たことが無い古道具屋だ
あの大きな机が売れたらしい
貧乏知りぬいた夫帰で 放哉
池にそっと浮いた葉だ
ほんの少しの赤さ見ゆる山茶花
下手医者の門から出て来た
枯木を叩けば虫が喰ってる
きかぬ薬を酒にしよう
茶わんの好きな模様を買ふ
なんかは入って居そうな壷だ
昔しは海であったと榾をくべる 昔は海であったと榾をくべる
半紙の皺をのばす
晩めしはやめて寝る 放哉
蜜柑一つで手紙入れて来てくれた
さんざん面白い眼をした皺よらしてゐる
かき餅半畳に干し足り
指輸が光る夜中のゆび
大きな番傘をあける
古足袋のみんな片足ばかり
朱筆もさしてある冬陽
曲りくねった道が海に出た
次ぎ次ぎ咲いてしまった花だ
宵月よ晩めし時 放哉
小便に起きて来る夜中の影だ
状袋にお銭をみんな入れとく
寒ン空シヤツポがほしいな
冬陽病んで寝て居る
饅頭をたべた大きな口だ
こんな町を電車が走って居る
女が下りた銀座だ
遥か新道をつくって居る
煙草店冬となり
工場の小さい裏門 放哉
布団のなかの肋骨がごろごろしとる
蜜柑たべてよい火にあたって居る
六銭張って小言云ってやる
泊り泊りの灯しつけて寝る
銭湯から神主が出て来た
飯前の手紙ポストに入れて来る
一日青空のまんまで暮れ切る
鍋釜つけてある冬の小流れ
とっぶり暮れて足を洗って居る
蜜柑の皮が火鉢のそばに置いてある 放哉
昼の鶏なく漁師の家ばかり
あけがたの風強し水汲む音
洗ったテーブルかけのうすいしみ跡
行く度かだまされた夜中の足音
夕べの凍て風に雄ん鶏なかであり
気に入った部屋に案内された
海凪げる日の大河を入れる
宿は暮れ切らぬ前の山見てる
栗のいが朝の下駄で踏みわる
雨になったぬくい寝床だ 放哉
晩の灯を入れた雨の宿屋町
まっ白い牛の乳をしぼる
読書す夜のうす霧
朝の白雲消えて大河
働きに行く人ばかりの電車
みんなが弁当箱をさげとる
日曜の洋服がぶら下がってる
田舎の月が遅く出て来た
柚子を一つもいで来るうす雪
煙草屋の娘のお白粉がはげてた
野道の風に立ち先生である
電柱突きさしてある山の畑
二度もなったよ宵の半鐘
河原火を焚きあげる冬が来た
子守唄に月が出て来た
昼間猫の子を捨てに出かける
大きな冬木が切られて居る
炬燵によい火を入れてくれた
雪の宿屋の金屏風だ
夜あけし港の船舶ある
わが家の前の冬木二三本 わが家の冬木二三本
ゆっくり歩いて行く夜霧の道
家鴨も女も太って居る
家のぐるり落葉にして顔出してみる
霜朝犬がくわえて来たもの
父子で芋堀る
山茶花に今日も霰が来る
家たてる材木が置かれ山茶花
夜のコーヒーを呑む男と女ばかり
一人の道が暮れて来た 放哉
句稿(29)
此ノ百句ハ非常ニ苦吟シマシタ、但、ホメテモラヱルノガ有ルカト心配シテマス
層雲雑吟 尾崎放哉
墓原小さい児が居る夕陽
墓の前に女が引っ付いてしまった
墓にもたれて居る背中がつめたい
墓原花無きこのごろ
墓原暮れて出る縁日
墓原昼の大きな提灯
赤ン坊ころがして大根が煮えた
ふた子かなし似て居る
泣いてるよ今朝生れた赤ン坊
赤ン坊一と晩で死んでしまった
淋しや壁張って居る
わが家近くなり児が駆け出す
兎を飼って貧乏してる
葱畑の大きな足跡
寒ン空火事がうつる
薮のなかの凍てきった路だ
朝眼がさめた児が唄ってる
暗い土間で足ふいてあがる
飯粒かたくなって居た袖口
茶わんがこわれた音が窓から逃げた 放哉
暗らくてなんにも読めない机だ
曇る陽の庭石案内される
ハガキが一枚ほり込んであった
山から小供あづかって来た
日が落ちた夜のペンサキ
夜釣からもどったこんな小さい舟だ 夜釣から明けてもどった小さい舟だ
曇り日の花切る忌日
夜の裏木戸ばたりばたりならし
手拭かたくしぼった朝陽
よく吹く事だな又夜になる 放哉
となりは未だ起きぬ霜朝
水車廻らぬ冬の家あり
今朝は俺が早かったぞ雀
おはぎを片寄らして児が提げて来た
柳散り散り尽したる小流れ
柳散りつくし風の日ばかり
朝々散る柳ある庭石
晩の小ざかな売りに来る女ばかり
一枚の舌を出して医者に見せる
行灯さげて来て二人の間に置く 放哉
この村で一人の兵隊さんだ
沈丁花の匂ひ夜中思ひ出してゐる
月夜のかるい荷物
よい凧一つ海にとられた
公園木枯の児等ばかり
児を連れて城跡に来た
城跡の大松吹き居り
大霜のわが家ばかり
朝の姿見からはなれる
大霜昼となるお針子 放哉
ばけつにいっぱい水汲めば足る
ていねいに読んで行く死亡広告
窓の下雨やどりして立ち去る
小窓の外から小供に呼ばれる
夕陽の座敷となる一本の柱
坊さんが奥の方から出て来た
橋もいっしょに渡って来て別れる
小犬が鳴いて居る風の夜もある
女だけ助かった朝の渚の話し
大浪晴るゝ朝なり
かたくり粉の湯がぬる過ぎた
少し風立ち晩の藁灰
いつもまっ黒い板の天井だ
インキ壺透かして見る
いやな手紙を噛んで居る女だ
土瓶のふたに皿が乗ってる
風吹く道のめくらなりけり 風吹く道のめくら
まき割る風つのる
一丁の冷豆腐たべ残し
古道具やの店はかなしく 放哉
絵はがきばかり出て来るカバンだ
汽車走る間のをもちや売り去れり
餅を喰ひくたびれたよい火がをこって居る
橋のきわのうまい寿司屋が無くなった
もう川舟が下り始めたらしい
夫婦で相談してる旅人とし 旅人夫婦で相談してゐる
又一人雪の客が来た
風呂吹きをよばれに行くよい月だ
今夜の分を出して置く白い丸薬
元日の灯に家内中の顔がある
元日のみんな達者馬も達者 放哉
思ひ出したやうに火がはねる
まってる蛙がこっそり出て来た顔だ
芸者の三味線かついで行く月夜
知った芸者に逢って煙草を捨てる
羽織を着ればひもがある
壁を張る新聞紙をわけてもらう
羽織のたもとには入って居った
漬物きざむ手で児を受取る
どかどか客が来たとなりの部屋
となりも静かな客だ 放哉
寝たがひの肩持ちて朝居る
朝の茶をつまみ風落ち
釘の手拭が氷って居るさま
朝々の土瓶煮え立ち
お聟さんに夕月光り
婚礼の夜の提灯に雪ふらし
婚礼からもどって少し酔ってる
カタクリ粉が落ちて居た朝の畳
女郎屋が一軒焼けの冬夜
鐘ついて来た顔で話す 放哉
句稿(30)
層雲雑吟 尾崎放哉
すっかり明け切って居る洗面器
嫁さんが来た淋しい町だ
ぬくい屋根で仕事して居る
佛に供える青い葉朝露にぬれ
となりの児にかきもち焼いて置く
墨つけた顔でもどって来た
なにかこわした音もしてたそがれ
蛙をつぶし蟹を殺した児がくたびれて居る
そっと石を起すうす濁り
灰かけて置いた火が夜中に出て来た 放哉
裸足に恋れたよ島の女
蜜柑を買わされ片眼を知らずに居た
赤インキを引っくりかやして夜が明けた
何かいっぱい書いてある手紙だ
児等が未だ遊んで居る一つの窓
釘にかけ切れないで輪かざりの庵り
夜中の雨を話して居る逗留客だ
戻ったらすぐ竹馬に乗って居る
絵のうまい児が遊びに来て居るよ 絵の書きたい児が遊びに来て居る
満潮の橋長々とかゝれり 放哉
ぶらぶら女と来た踏切り
暮れ方の裾に綿がついて居た
夕陽の小窓があけてある
見世物小星がばた/\片付けとる
山風山を下りるとす
山火事の北国の大空
庭石皆少ししめりたる
新藁散らかして仕事してゐた
小さいランプで勉強してゐる
朝の高塀に沿ふて働きに出る
うす霜の朝の切戸があいてる
さめたコーヒー皿で待ってる
コゝア呑む腕がはち切れそうだ
ちらと見た知らぬ顔で過ぎた
朝の踏切のうす靄
踏切りどっかで鶯が啼いとる
雨の汽章路ばかり踏切
踏切に来れば浪音
大根ぶら下げて止められた踏切
まるい山の肩に宵月が乗ってる
山路はいろ/\の落葉
落葉焚きあげ呼ばれて居る
落葉焚きあげ大木
雪に小便する児等は並び
土間が奇れいに掃いてある
小さい銀杏の木が真ツ黄になり
帽子あみだにして陽にやけて居る
暗い土間で仕事して居た
落書が無くてお寺の白壁
一寸書き付けて置いた紙切れが無い
釘の手拭が一日乾かぬ
夜のお茶がぶがぶ呑むよく呑む
留守番の小供は寝とる
芽ぶくもの見てまはるある日
まだ明かるい空に親しみ
海見えはぢめ風吹くなり
一人住みてあけにくい戸ではある
夜中の蜜柑一つたべる
眼の前する/\と帆をあげた船
今年は雨風多し乞食
夜の襖があけてあった
銀貨が一枚交って居た
宵の口の喧嘩話しで銭湯
茶の花時雨れるのか
雀が来る木が切られてしまった
大根畑から出た月だ
お医者の靴がよく光ること
橋を渡る提灯が一つ
山が冷えて来た凧下ろす
曇り日の鉛筆をけづる
さら/\浪よす渚薄氷
恋のうたばかり唄ひ里の遠い火
月夜の葦が析れとる
めざしを焦がしてしまった
冬は白雲の光り
雪の山見ては書く手紙
あいてる椅子にかけてあついコーヒーだ
草に陽がはいる大きなタンク(満州長春)
やすい馬車の冬陽走らす(同所) 放哉
大きな池の風に立ち地図をひろげる
静かなる鶴の一本の足
池に座敷を浮べ鯉をたべさせる
小さい池に出て弁当たべる
鯉がはねる音の貧厨
同じやうな沼の景色漕ぎ出で
大きな沼の枯れ葦
弟とふるさとの池の風に立つ
池のぐるりは白雲ばかり
鮒釣る池の風が強い 放哉
今朝の障子を郵便やがあけた
大霜月は雲となり
枯れ枝が動いて居る
鮒がたくさん釣れる雪風となり
どうしても動かぬ牛が小便した
一日森で遊んでしまった
森をわけ入り小供になる
よどんで居るお椀を流してやる
意地悪るの児をにくむ心があった
夜が明け切って居る町の小流れ 放哉
句稿(31)(注)井泉水によって三月25日着と記されている。
層雲雑吟 尾崎放哉
雀がたった二つ居る夫帰らしい
雨水の流れ動く朝の庭
一日雪がふりつゞける障子
誰か居るらしいまっ白い障子
雪国の元気な小供等だ
牡丹雪となったたそがれ
この宿鳩を飼って居たのか
夕風葉と吹かるゝ虫あり
墓のうらに廻る
わが夜の雪ふりつもる
アナタの(わらやね雪ふりつもる)・・・が、常に思い出され、真似して見たのですが?
四角な庵の元日
ことこと番茶を煮てもてなす
遠くの餅つく音で起こされて居る
つきたての餅をもらって庵主であった
夜中の天井が落ちて来なんだ
のびたあごひげのさきを焦がして居る
たもとになんにもは入って居ない
星がふるやうな火の見やぐら
冬の海には遠く船一つ 放哉
大晦日皆松にとり変へて佛の花
あすは元日が来る佛とわたくし
餅をもらった白砂塘ももらった
どっから夜中の風がは入って来るのか
和尚さん木鋏をならし訪ねて居る
大晦日暮れた掛取も来てくれぬ 掛取も来てくれぬ大晦日も独り
墓を拝む兄のうしろ
一番鶏がないたやうでもある欠伸をした
朝方の大雨を知らずよい晴れだ
お月さんもたった一つよ 放哉
大いなる人この山奥にかくれしと
風烈しき夜々のランプ灯もされ
石油たっぷりついでランプの夜である
ランプ灯もす頃の船がは入って来る
二三人にランプが灯もされるランプ掃除の油手をふく残雪
雪積もる夜の燃え座はるランプ 雪積もる夜のランプ
ランプの笠に粉雪の音するよ
ランプの笠がかしげとる 放哉
枯れあし明けて居るそれだけ
貸家気に入らないで出る秋草
いつもよい花活けて迎える
フト曇り来る部屋に居たり
窓に肱を置く大地の春
窓から手をのばして拾ふ
月光の井戸を覗いただけだ
さっき出て行った音がした
不格好な石の冬
星がふるやうな山の道
神の朝の木木立ち
落ち葉曇り日をとべり
まっ黒な顔で惚れられた
坂の雨流れ青空
皿のお菓子が一つになっとる
夕づつ妻から児を抱きとる
手洗鉢の落葉かきわけ水
木の実ころころ見えなくなった
雨の舟岸により来る
行き違ひの日曜を訪ね
網干す雫砂に落つ
木引きがとう/\引き切った
山奥木引き男の子連れたり
山の木引きがこゝの生れでなかった
夏の夜の茶わん音さして買ふ
白きめしほ気立てゝ朝の茶わん
いつしか自分の茶わんとなり
台所しまうをそい灯
友の絵がうまいんだそうだ
電気がぶら下がって居た机にもどった
手毬がとび込んで来た内庭しんかん
芝居の幕合に蚊にくはれた
貧乏の軒を押し並べ夕陽
南瓜半分喰はれて居る
雨に濡れ雨を流し冬木
背中で泣く児わが児よ
お金がほしそうな顔して寒ン空
足袋洗ふ朝の雪晴れ
落葉踏み来し宮のうしろ
山の匂ひ嗅ぎ行く犬の如く
夕空見てから晩めしにする 夕空見てから夜食の箸とる
行き止りの道なりき落ち葉
明け方ひそかなる波よせ ひそかに波よせ明けてゐる
水たまりをとんで行った児だ
名刺を張ってわが家とす
昼の波音になれたるさへ
冬木の窓があちこちあいてる
窓あけた笑ひ顔だ
潮くさい夫婦で児を太らせる 放哉
日が暮れても大根つけとる
硯の水がちんまり澄んで居た
芝居もどりがくしやみして通る
冬月外套のボタンをはめる
夕空の下の夫婦
冬山登ればお城が見える
船の待合所で呑んでる
西洋人の長い足が乗ってる人力だ
梯子上ったり下りたり暖い
白壁雨のあとある 放哉
ページトップ
|