科学の色>ベニ
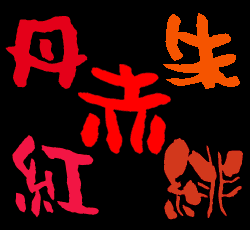
ベニの謎(1)
新年なので、めでたい紅(アカ)のお話。日本においては、アカは赤が主流であり、一部「紅白」「口紅」「紅葉」等で使用されている。 中国では、「紅十字」(赤十字)、「紅一点」(王安石の詩『詠柘榴』)等々アカ色の表現には、紅の字を使用しているようだ。 さらに、アカ色の表す文字は他に「丹」「朱」「緋」等があり、わかりにくい。
「古代の朱」(松田壽男)によると、"古代の日本人が用いた朱(アカ)は赭(ソホ)と真赭(マソホ)の2種類。 赭はベンガラ、真赭は硫化水銀朱砂・・・"としている。(染料のアカネが抜けている?)
ベンガラは、当然和語ではなくインドのベンガルを語源としていることは承知のところ。 江戸時代、東インド会社あたりが持ち込み、舶来の優秀さ故、それまでの丹・鉄丹・代赭の言い方を駆逐したと思われる。
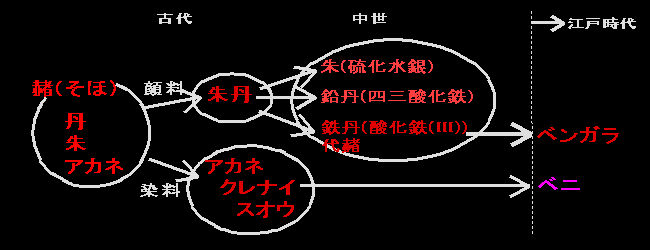
全く同様のことが古代にも起こっている。アカネに代わる紅(クレナイ)である。 呉(クレ)の藍(アイ)は遠い異国に対する憧れかもしれない。
ここで問題! 「べに」の響きがどうも和語に思えない。 万葉集では、紅(クレナイ)や末摘花(スエツムハナ、紅花)がうたわれているが、「べに」は見あたらない。
「べに」はいつ頃から使われだしたのだろうか。「べに」の語源はなんなんだろうか。調査してみる価値あり!
(2010/1/17、TAKA)
ベニの謎(1)|ベニの謎(2)|ベニの謎(3)|ベンガル、ベンガラ、ベニガラ|ベンガラの謎(1)|ベンガラの謎(2)|ベンガラの謎(3)| ベンガラの謎(4)|ベンガラの謎(5)|
幻の反魂丹|丸、散、丹|丹(タン)と丹(ニ)|
トップページへ